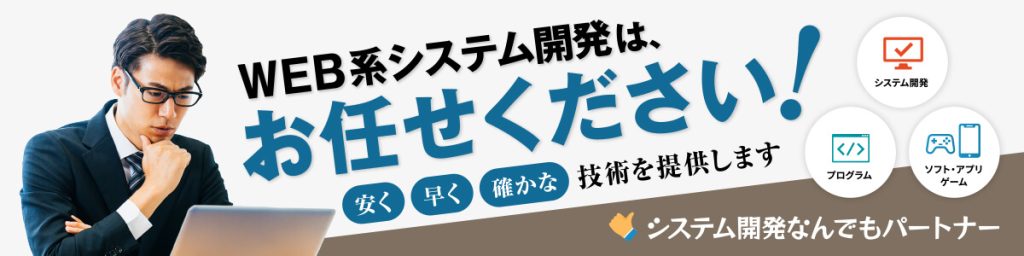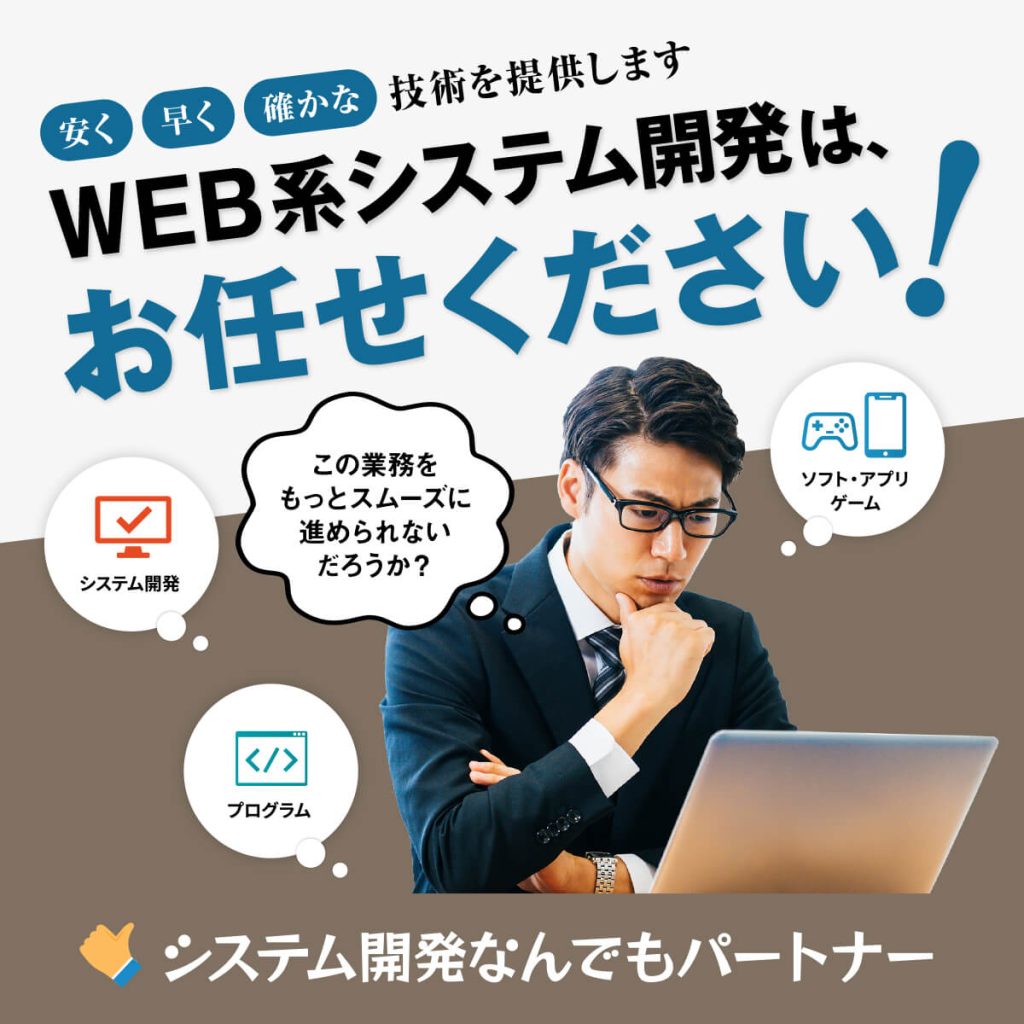サーバー管理者としてのスキルをさらに向上させるために、専門用語を引き続き紹介します。これらを知っておけば、業務効率がアップするだけでなく、トラブルシューティングの際にも役立ちます。
1. IaaS(Infrastructure as a Service)
サーバーやネットワーク機器、ストレージなどをクラウド上で提供するサービス形態。例: AWS、Microsoft Azure。
2. RAID(Redundant Array of Independent Disks)
複数のハードディスクを組み合わせ、データを分散保存する仕組み。冗長化や高速化を目的として利用されます(例: RAID 0, RAID 1, RAID 5)。
3. コンテナ化(Containerization)
アプリケーションとその依存関係をパッケージ化し、どこでも動作可能にする技術。Dockerが代表例です。
4. ホットスワップ(Hot Swap)
システムを停止せずにハードウェアを交換できる技術。特に高可用性を求められるサーバーで重要です。
5. シャーディング(Sharding)
データベースを分割し、複数のサーバーに分散して保存する方法。大量データの処理速度を向上させるために用います。
6. スケールアウト(Scale Out)
システムの性能向上を目的として、サーバーの台数を増やす手法。クラウド環境でよく使用されます。
7. スケールアップ(Scale Up)
既存のサーバーにCPUやメモリを追加し、性能を強化する方法。
8. プロビジョニング(Provisioning)
サーバーやリソースを利用可能な状態に設定するプロセス。自動化ツールとしてTerraformが有名です。
9. バックプレッシャー(Back Pressure)
システムが過負荷状態に陥るのを防ぐため、データの流れを調整する仕組み。メッセージングシステムやストリーム処理で重要です。
10. ローリングアップデート(Rolling Update)
稼働中のシステムを停止させずに、順次アップデートを行う手法。ダウンタイムを最小限に抑えます。
11. ゾーニング(Zoning)
ストレージネットワーク(SAN)内でデバイス間の通信を制限することで、セキュリティやパフォーマンスを向上させる手法。
12. ハイパーバイザー(Hypervisor)
仮想マシンを管理・運用するためのソフトウェア。種類として、Type 1(ハードウェア直結型)とType 2(ホスト型)があります。
13. トランザクションログ
データベースでの変更内容を記録したログ。障害発生時のデータリカバリに役立ちます。
14. エラスティックIP(Elastic IP)
クラウドサービスで提供される固定IPアドレス。動的なインフラ環境でも安定した接続が可能です。
15. セマフォ(Semaphore)
システムのリソースを制御するための仕組み。並列処理やマルチスレッド環境で利用されます。
まとめ
サーバー管理者として覚えておくべき用語は多岐にわたりますが、基本から応用まで理解することで、より効果的なシステム運用が可能になります。今回紹介した用語もぜひ実務に活かしてください!