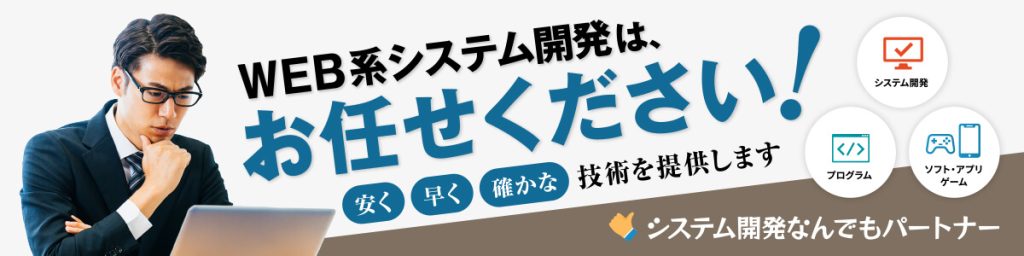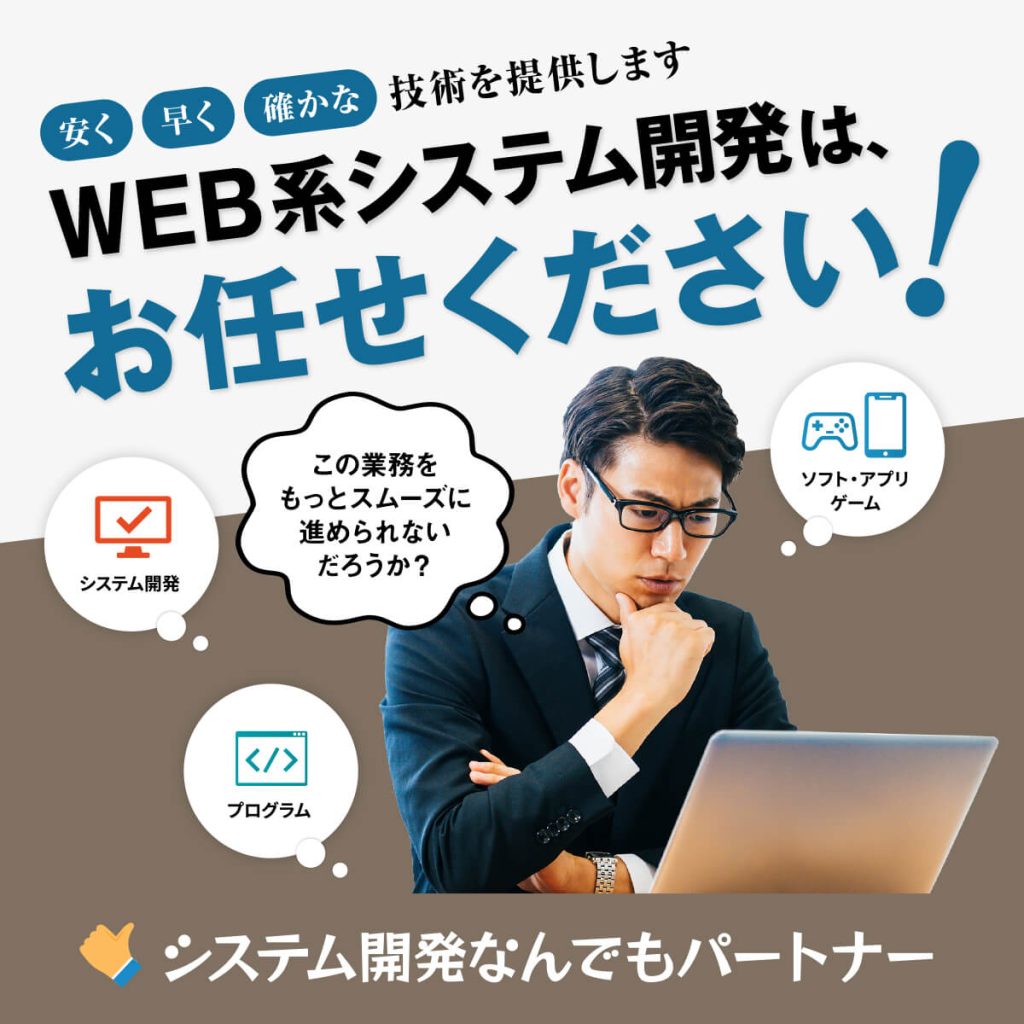システム開発の成否は、最初の「要件定義」に大きく左右されます。要件定義が曖昧だと、開発途中で仕様変更が多発し、スケジュール遅延やコスト増大を招くことになります。本記事では、失敗しないための要件定義のベストプラクティスを紹介します。
要件定義とは何か?
要件定義とは、システムに求められる機能や仕様、制約を明確にする工程です。要件は大きく「業務要件」「機能要件」「非機能要件」の3つに分類されます。
- 業務要件:システムが実現すべき業務プロセスやビジネスゴール
- 機能要件:具体的な機能や画面の仕様、データの入出力など
- 非機能要件:セキュリティ、パフォーマンス、拡張性、保守性など
要件定義でよくある失敗例
ユーザーの要望が不明確
開発者と利用者の認識がズレたまま進行し、後から「想定と違う」と言われるケースです。
対策:
- 初期段階でユーザーとワークショップを実施
- プロトタイプを作成し、具体的なイメージを共有
仕様変更が頻発する
開発途中で要件が頻繁に変わり、プロジェクトが迷走することがあります。
対策:
- 要件凍結のルールを定める(変更は影響分析後に判断)
- 最低限の機能でリリースするMVP(Minimum Viable Product)を活用
非機能要件が考慮されていない
性能要件やセキュリティ要件が定義されていないと、リリース後にシステムが耐えられないことがあります。
対策:
- パフォーマンス要件(最大同時接続数など)を数値で定義
- セキュリティ要件を明記(認証方式やデータ暗号化)
要件定義のベストプラクティス
関係者全員を巻き込む
システムの最終ユーザー、IT部門、経営層など、すべての関係者を要件定義の段階で巻き込み、認識のズレを防ぎます。
ユースケースを明確にする
利用シナリオを具体化することで、要件が整理され、後から「使えない」システムになることを防げます。
変更管理プロセスを明確にする
仕様変更の際にどのような手続きを経るのか、あらかじめ決めておくことで、開発の混乱を防げます。
まとめ
要件定義の精度が、システム開発の成功を左右します。関係者との密な連携、明確な仕様の文書化、変更管理の徹底を心がけることで、失敗を防ぐことができます。ぜひ、今回のベストプラクティスを活用し、効果的な要件定義を行ってください。