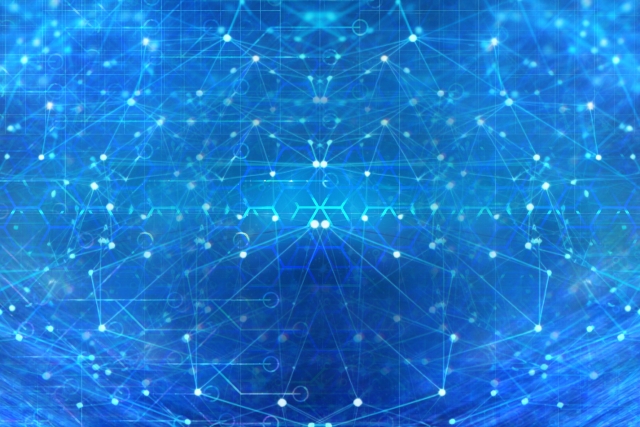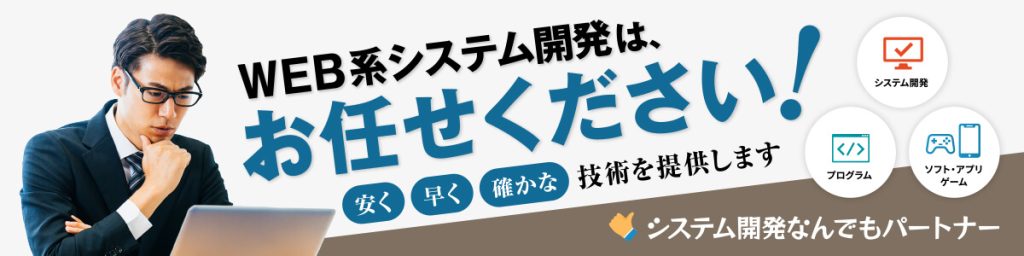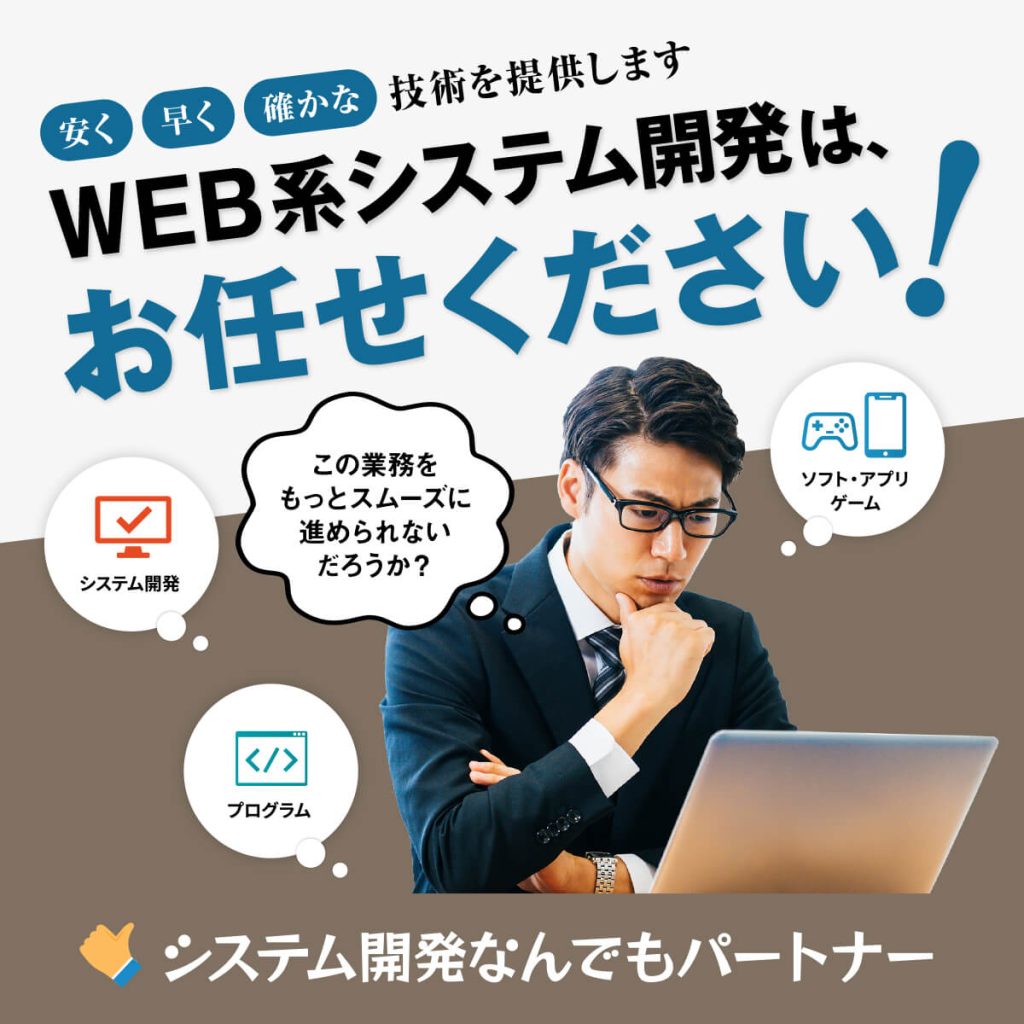サーバー管理者として新たなキャリアをスタートしたばかりの方にとって、専門用語を正しく理解し活用することは、業務を円滑に進めるうえで欠かせません。ここでは、入社後すぐに覚えておきたいサーバー管理者向けの基本的な専門用語を紹介します。
1. IPアドレス
インターネットやネットワーク上のデバイスを特定するための一意の識別番号。IPv4とIPv6の2種類があります。
2. DNS(Domain Name System)
ドメイン名(例: example.com)をIPアドレス(例: 192.168.1.1)に変換する仕組み。ウェブサイトへのアクセスを可能にします。
3. SSH(Secure Shell)
サーバーにリモートで安全にアクセスするためのプロトコル。公開鍵と秘密鍵を利用して認証を行います。
4. HTTP/HTTPS
ウェブブラウザとサーバー間でデータをやり取りするためのプロトコル。HTTPSは通信を暗号化した安全なバージョンです。
5. CLI(Command Line Interface)
サーバー管理に欠かせないコマンド入力による操作方法。LinuxやUnix系OSでは特に頻繁に使用します。
6. ファイアウォール
ネットワークを保護するために、特定のトラフィックをブロックまたは許可するセキュリティシステム。
7. ロードバランサー
複数のサーバー間でトラフィックを分散し、システムの負荷を最適化する仕組み。高可用性を実現します。
8. 仮想化(Virtualization)
1台の物理サーバー上で複数の仮想サーバーを作成し、リソースを効率的に利用する技術。代表例はVMwareやKVM。
9. コンテナ(Container)
アプリケーションとその依存関係をパッケージ化した軽量な仮想化技術。Dockerが代表的。
10. ログファイル
サーバーの動作記録が保存されたファイル。トラブルシューティングやセキュリティ監視に利用します。
11. プロキシサーバー
クライアントとサーバーの間に立ち、通信を仲介するサーバー。アクセス制限やキャッシュ機能を提供します。
12. RAID(Redundant Array of Independent Disks)
複数のディスクを組み合わせてデータの冗長性や速度を向上させる仕組み。RAID 1(ミラーリング)やRAID 5が一般的。
13. バックアップ
サーバーデータを定期的にコピーし、万が一の障害時に復旧できるようにする仕組み。
14. NTP(Network Time Protocol)
サーバーやネットワークデバイスの時刻を同期するためのプロトコル。正確な時刻はログ管理やシステム運用に重要です。
15. スケーリング(Scaling)
サーバーのリソースを増減させて負荷に対応する方法。水平スケーリング(サーバー台数の増加)と垂直スケーリング(リソースの強化)があります。
16. キャッシュ
頻繁に使用されるデータを一時的に保存し、アクセス速度を向上させる仕組み。ウェブサーバーやブラウザで使用されます。
17. SSL/TLS
データ通信を暗号化して安全性を確保するプロトコル。TLSはSSLの進化版です。
18. Cronジョブ
Linuxサーバーで定期的に特定のタスクを自動実行するためのスケジュール管理ツール。
19. デーモン(Daemon)
バックグラウンドで動作するサーバープロセス。例: ApacheやMySQLなど。
20. セキュリティパッチ
脆弱性を修正するためのソフトウェアアップデート。定期的に適用してセキュリティを保つことが重要です。
まとめ
これらの基本用語を理解することで、サーバー管理の基礎が固まり、業務をスムーズに進められるようになります。新しい言葉に出会った際は、その都度調べ、実践での理解を深めていきましょう。